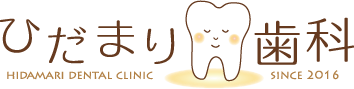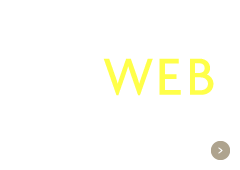差し歯と被せ物の違い:正しく理解して最適な治療を選ぼう

はじめに
歯科治療の説明を受ける際、「差し歯」や「被せ物」という言葉を耳にすることがあります。多くの方がこれらを同じものと考えていますが、実は明確な違いがあります。正しい知識を持つことは、自分に合った治療法を選択する上で非常に重要です。この記事では、差し歯と被せ物の違いを詳しく解説し、それぞれの治療が適している状況、メリットとデメリット、費用の目安までご紹介します。歯科治療に対する理解を深め、納得のいく選択ができるようサポートします。
差し歯とは
差し歯の定義
差し歯とは、歯の根だけが残っている状態で、人工の歯を差し込むように装着する治療法です。正式には「ポストクラウン」と呼ばれ、歯根に土台(コア)を立て、その上に被せ物(クラウン)を装着します。歯の頭の部分がほとんど残っていない場合に適用される治療法です。
差し歯の構造
差し歯は二つの部分から構成されています。一つ目は、歯根に差し込む土台(ポスト)です。これは金属製やファイバー製のものがあり、歯根管に挿入して固定します。二つ目は、その土台の上に装着する被せ物(クラウン)です。この二段階の構造により、歯根だけの状態から歯の形態を回復させます。
差し歯が必要なケース
虫歯が深く進行して歯の大部分が失われた場合、歯が折れて歯冠部がほとんどなくなった場合、根管治療後に歯質がほとんど残っていない場合などに差し歯が選択されます。歯根がしっかりしていることが前提条件となります。
被せ物(クラウン)とは
被せ物の定義
被せ物は、歯を全体的に覆うように装着する人工の歯冠です。クラウンとも呼ばれ、歯の形を回復させながら強度を補強する役割を果たします。歯の頭の部分がある程度残っている状態で、その歯を削って形を整え、上から被せるように装着します。
被せ物の構造
被せ物は基本的に一体構造で、削った歯の上に直接被せます。土台を別に作る必要がない点が差し歯との大きな違いです。ただし、歯質が大きく失われている場合は、被せ物の前に土台を作ることもあり、この場合は差し歯に近い構造になります。
被せ物が必要なケース
虫歯が広範囲に及んでいるが歯質がある程度残っている場合、歯が欠けたり割れたりしたが歯冠部が残っている場合、根管治療後でも歯質が十分に残っている場合、歯の形や色を大きく変えたい場合などに被せ物が選択されます。
差し歯と被せ物の主な違い
適用される歯の状態
最も重要な違いは、残っている歯質の量です。差し歯は歯根だけが残っている状態で適用され、被せ物は歯冠部がある程度残っている状態で適用されます。つまり、残っている歯の量によって治療法が変わります。
治療の工程
差し歯は、まず歯根に土台を立て、その後被せ物を装着するという二段階の工程が必要です。一方、被せ物は歯を削って形を整え、その上に直接被せるという一段階の工程で済むことが多いです。ただし、歯質の状態によっては被せ物でも土台が必要になることがあります。
強度と耐久性
差し歯は土台と被せ物の接合部分があるため、被せ物のみの場合と比較すると、やや破折のリスクが高くなります。特に金属製の土台は硬すぎて歯根を割ってしまうリスクがあります。被せ物は残存歯質に直接接着されるため、比較的強度が保たれやすい傾向があります。
費用の違い
差し歯は土台と被せ物の両方を作製する必要があるため、工程が多く、一般的に被せ物のみの場合よりも費用が高くなります。ただし、保険適用の範囲内であれば、どちらも比較的安価に治療を受けることができます。
土台の種類と特徴
メタルコア(金属製の土台)
従来から使用されている金属製の土台です。保険適用で安価に作製できますが、硬すぎるため歯根が割れるリスクがあります。また、金属アレルギーの原因となることや、歯茎が黒ずむ原因となることもあります。前歯に使用すると、金属の色が透けて見えることがあります。
ファイバーコア(グラスファイバー製の土台)
グラスファイバーとレジンで作られた白い土台です。歯根と同程度の弾性を持つため、歯根破折のリスクが低く、審美性にも優れています。金属アレルギーの心配もありません。ただし、自由診療となることが多く、費用はメタルコアより高額になります。1本あたり約1万円から3万円程度が相場です。
レジンコア
レジンで作る土台で、保険適用が可能です。メタルコアよりも歯に優しいとされていますが、強度はやや劣ります。小臼歯や前歯など、比較的負担の少ない部位に適しています。
被せ物の種類と特徴
保険適用の被せ物
保険適用の被せ物には、金銀パラジウム合金製の銀歯、レジン前装冠(前歯用で表側だけ白いもの)、CAD/CAM冠(条件を満たせば使用できる白い被せ物)などがあります。費用は1本あたり約3000円から1万円程度と安価ですが、審美性や耐久性には限界があります。
自由診療の被せ物
自由診療では、オールセラミック、ジルコニアセラミック、メタルボンド、ゴールドなど、様々な材料が選択できます。審美性、耐久性、生体親和性に優れていますが、費用は1本あたり約5万円から20万円程度と高額になります。
差し歯と被せ物の寿命
一般的な寿命
保険適用の差し歯や被せ物の寿命は約5年から7年とされています。自由診療のセラミックやジルコニアを使用した場合は、10年以上持つことも珍しくありません。ただし、これらは適切なメンテナンスを行った場合の目安です。
寿命を延ばす方法
毎日の丁寧な歯磨き、デンタルフロスの使用、定期的な歯科検診とクリーニング、硬いものを噛まない、歯ぎしりや食いしばりへの対策などにより、差し歯や被せ物の寿命を延ばすことができます。特に定期検診では、被せ物の適合状態や土台の状態をチェックしてもらうことが重要です。
トラブルのサイン
被せ物や差し歯に違和感がある、噛むと痛い、歯茎が腫れる、被せ物が動く、口臭が気になるなどの症状がある場合は、すぐに歯科医院を受診しましょう。早期に対処することで、抜歯を避けられる可能性が高まります。
治療を受ける際の注意点
歯根の状態確認
差し歯や被せ物の治療を受ける前に、歯根の状態をしっかり確認することが重要です。歯根が割れている、根の先に炎症がある、歯根が短すぎるなどの問題がある場合、治療ができないこともあります。レントゲン検査やCT検査により、正確な診断を受けましょう。
根管治療の重要性
差し歯を入れる際は、必ず根管治療が必要です。根管治療が不十分だと、後から痛みや腫れが生じ、やり直しになることがあります。根管治療は時間がかかることもありますが、丁寧に行ってもらうことが重要です。
審美性と機能性のバランス
前歯など見える部分は審美性を重視し、奥歯など見えにくい部分は強度を重視するなど、部位に応じて材料を選択することも一つの方法です。すべてを最高級の材料にする必要はなく、予算と相談しながら優先順位をつけることも大切です。
セカンドオピニオン
高額な治療を提案された場合や、治療方針に疑問がある場合は、他の歯科医院でセカンドオピニオンを受けることも検討しましょう。複数の意見を聞くことで、より納得のいく選択ができます。
インプラントという選択肢
歯根も失われている場合や、歯根の状態が悪く差し歯が難しい場合は、インプラントという選択肢もあります。インプラントは人工の歯根を顎の骨に埋め込み、その上に被せ物を装着する治療法です。周囲の健康な歯を削る必要がなく、自然な噛み心地を得られるというメリットがあります。ただし、外科手術が必要で、費用も高額になります。
まとめ
差し歯と被せ物は、似ているようで明確な違いがあります。差し歯は歯根だけが残っている状態で土台を立てて被せ物をする治療、被せ物は歯質がある程度残っている状態でその上に直接被せる治療です。どちらの治療が適しているかは、残っている歯質の量によって決まります。治療を受ける際は、歯の状態をしっかり診断してもらい、土台や被せ物の材料についても十分に説明を受けましょう。保険診療と自由診療のそれぞれにメリットとデメリットがあるため、予算や希望する審美性、耐久性などを考慮して、歯科医師とよく相談しながら最適な治療法を選択することが大切です。適切な治療とメンテナンスにより、長く快適に使い続けられる歯を手に入れましょう。
お子様にもおすすめ!怖くない、痛くない、安心して通える、優しいスタッフと楽しい雰囲気の歯科医院です。
ひだまり歯科、是非、ご来院ください。