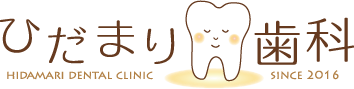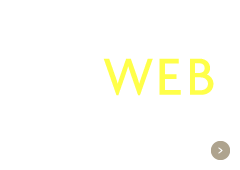口呼吸がもたらす悪影響:鼻呼吸に切り替えて健康を取り戻そう

はじめに
無意識のうちに口で呼吸していることはありませんか。実は口呼吸は、想像以上に多くの健康問題を引き起こします。本来、人間は鼻で呼吸するように設計されており、鼻呼吸には空気の加湿、浄化、温度調整など、様々な重要な機能があります。しかし、現代では多くの人が口呼吸になっており、それが原因で口腔内の健康だけでなく、全身の健康にまで悪影響を及ぼしています。この記事では、口呼吸がもたらす具体的な悪影響と、その原因、そして鼻呼吸に改善する方法について詳しく解説します。自分や家族の呼吸習慣を見直し、健康的な生活を取り戻しましょう。
口呼吸とは
口呼吸とは、文字通り口で呼吸することです。本来、呼吸は鼻で行うべきものですが、鼻づまりや習慣により、口で呼吸するようになってしまうことがあります。特に就寝中は無意識のうちに口呼吸になっていることが多く、朝起きた時に口の中が乾燥している、喉が痛いといった症状がある場合は、口呼吸をしている可能性が高いです。
子どもの場合、いつも口が開いている、よだれが出やすい、いびきをかくなどのサインが見られます。大人でも、マスクをしていると息苦しくて口呼吸になってしまう方が増えています。
鼻呼吸の重要な役割
口呼吸の悪影響を理解する前に、まず鼻呼吸の重要性を知る必要があります。鼻には優れたフィルター機能があり、空気中のホコリ、細菌、ウイルスなどを除去します。鼻毛や粘膜がこれらの異物を捕らえ、体内への侵入を防ぎます。
また、鼻腔を通ることで空気が加湿され、適度な湿度を保った状態で肺に届きます。さらに、冷たい空気も体温に近い温度まで温められるため、気管や肺への刺激が軽減されます。鼻呼吸により、一酸化窒素という物質が産生され、これが血管を拡張して酸素の取り込みを促進する働きもあります。
口呼吸がもたらす口腔内への悪影響
虫歯と歯周病のリスク増加
口呼吸により口腔内が乾燥すると、唾液の量が減少します。唾液には、口腔内を洗浄する自浄作用、細菌の繁殖を抑える抗菌作用、歯を修復する再石灰化作用など、重要な働きがあります。口呼吸によりこれらの機能が低下すると、虫歯や歯周病のリスクが大幅に高まります。
朝起きた時に口の中がネバネバしている、口臭が強いという症状は、口呼吸による口腔内の乾燥が原因の可能性があります。
歯並びと顔貌への影響
特に成長期の子どもが口呼吸を続けると、顎の発育に悪影響を及ぼします。口が常に開いている状態では、舌の位置が下がり、上顎の成長が不十分になります。その結果、歯並びが悪くなったり、顔が細長く伸びたりする、いわゆるアデノイド顔貌と呼ばれる特徴的な顔つきになることがあります。
出っ歯や受け口、顎が小さくなるなどの問題も生じやすく、将来的に矯正治療が必要になることも少なくありません。
口内炎ができやすくなる
口腔内の乾燥により粘膜が傷つきやすくなり、口内炎ができやすくなります。また、傷の治りも遅くなるため、口内炎が長引いたり繰り返したりすることがあります。
味覚への影響
唾液の減少により、味を感じる機能も低下します。食べ物の味物質が唾液に溶けて味蕾に届くことで味を感じるため、口腔内が乾燥していると味覚が鈍くなります。
口呼吸がもたらす全身への悪影響
風邪やインフルエンザにかかりやすくなる
鼻のフィルター機能を使わず、直接口から空気を吸い込むことで、細菌やウイルスが喉に直接侵入します。また、口腔内が乾燥することで粘膜のバリア機能が低下し、感染症にかかりやすくなります。口呼吸の人は、鼻呼吸の人に比べて風邪を引きやすいという研究結果もあります。
アレルギー症状の悪化
口呼吸により、アレルゲンが直接体内に入りやすくなります。また、口呼吸自体が鼻づまりを悪化させる悪循環を生み出すこともあります。花粉症やハウスダストアレルギーのある方は、口呼吸により症状が悪化する可能性があります。
睡眠の質の低下
口呼吸は、いびきや睡眠時無呼吸症候群の原因となります。口が開くことで舌が喉の奥に落ち込みやすくなり、気道が狭くなります。これにより、十分な酸素が取り込めず、睡眠の質が低下します。朝起きても疲れが取れない、日中眠気が強いという症状がある場合、口呼吸が原因かもしれません。
集中力や学習能力の低下
睡眠の質が低下することで、日中の集中力や記憶力が低下します。特に成長期の子どもの場合、口呼吸による慢性的な酸素不足が、学習能力や発達に悪影響を及ぼす可能性があります。
姿勢への影響
口呼吸をするために、無意識のうちに顎を前に突き出す姿勢になります。これが猫背や首の前傾姿勢につながり、肩こりや頭痛の原因となります。姿勢の悪化は、さらに様々な身体的不調を引き起こす可能性があります。
口臭の悪化
口腔内の乾燥により細菌が繁殖しやすくなり、強い口臭の原因となります。朝起きた時だけでなく、日中も口臭が気になる場合は、口呼吸が原因の可能性があります。
口呼吸になる原因
鼻づまり
アレルギー性鼻炎、慢性副鼻腔炎、鼻中隔湾曲症など、鼻の病気により鼻で呼吸することが困難になると、口呼吸になります。これらの原因を治療することが、口呼吸改善の第一歩です。
扁桃腺やアデノイドの肥大
特に子どもの場合、扁桃腺やアデノイドが大きくなることで気道が狭くなり、口呼吸になることがあります。いびきがひどい、睡眠中に呼吸が止まるなどの症状がある場合は、耳鼻咽喉科を受診しましょう。
習慣
最初は鼻づまりなどの理由があって口呼吸になったとしても、治った後も習慣として口呼吸が続いてしまうことがあります。無意識のうちに口が開いているという場合は、意識的に鼻呼吸を練習する必要があります。
口腔周囲筋の弱さ
口の周りの筋肉が弱いと、口を閉じておくことが難しくなります。特に子どもの場合、柔らかいものばかり食べていると、口腔周囲筋が十分に発達せず、口呼吸になりやすくなります。
鼻呼吸に改善する方法
原因疾患の治療
鼻づまりがある場合は、まず耳鼻咽喉科を受診し、原因を特定して治療を受けることが重要です。アレルギー性鼻炎の場合は薬物療法、鼻中隔湾曲症の場合は手術など、原因に応じた適切な治療があります。
鼻呼吸を意識する
日中、意識的に口を閉じて鼻で呼吸するよう心がけましょう。最初は難しく感じるかもしれませんが、繰り返すことで徐々に習慣化できます。仕事中や勉強中など、集中している時ほど口が開きやすいため、定期的に意識することが大切です。
口テープの使用
就寝中の口呼吸を防ぐために、専用の口テープを使用する方法があります。口に縦に貼ることで、口が開くのを防ぎ、鼻呼吸を促します。ただし、鼻が完全に詰まっている状態では使用しないでください。また、最初は違和感があるため、少しずつ慣らしていくことが大切です。
口腔周囲筋のトレーニング
口の周りの筋肉を鍛えることで、自然に口を閉じておけるようになります。あいうべ体操という簡単なトレーニングがあります。「あー」「いー」「うー」「べー」と大きく口を動かすだけで、口腔周囲筋を鍛えられます。1日30回程度、毎日続けることで効果が現れます。
舌の位置を意識する
正しい舌の位置は、舌先が上の前歯の裏側の歯茎に軽く触れている状態です。この位置を保つことで、自然と口が閉じ、鼻呼吸がしやすくなります。舌の位置を意識する習慣をつけましょう。
よく噛んで食べる
食事の際によく噛むことで、口腔周囲筋が鍛えられます。柔らかいものばかりでなく、歯ごたえのある食材も取り入れ、しっかり噛む習慣をつけましょう。
子どもの口呼吸への対応
子どもの口呼吸は、成長に大きな影響を与えるため、早期に対処することが重要です。いつも口が開いている、いびきをかく、よだれが多いなどのサインに気づいたら、小児歯科や耳鼻咽喉科を受診しましょう。
家庭でできる対策としては、食事をよく噛むよう促す、鼻呼吸を意識させる、口腔周囲筋のトレーニングを一緒に行うなどがあります。無理に口を閉じさせるのではなく、楽しみながら習慣を変えていくことが大切です。
まとめ
口呼吸は、虫歯や歯周病、歯並びの悪化など口腔内の問題だけでなく、風邪を引きやすくなる、睡眠の質が低下する、集中力が低下するなど、全身の健康にも深刻な影響を及ぼします。鼻づまりなどの原因疾患がある場合は適切な治療を受け、習慣として口呼吸になっている場合は意識的に鼻呼吸に切り替える努力が必要です。口テープの使用や口腔周囲筋のトレーニングなど、日常でできる対策を取り入れましょう。特に子どもの口呼吸は成長に大きく影響するため、早期発見・早期対応が重要です。鼻呼吸を習慣化することで、口腔内の健康だけでなく、全身の健康状態が改善されます。今日から自分や家族の呼吸習慣を見直し、健康的な鼻呼吸を取り戻しましょう。
治療内容をしっかりとご説明し、納得して頂くことで怖くない歯科医院を目指します!
阿倍野区昭和町おすすめ、ひだまり歯科、是非ご来院ください。