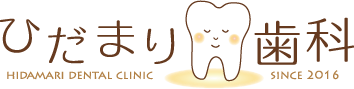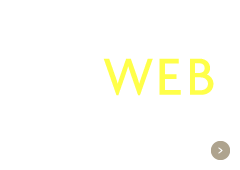根管治療とは?痛みはある?:歯の神経治療を徹底解説

はじめに
「神経を取る治療」と聞いて、不安を感じたことはありませんか。根管治療は、正式には「根管治療」または「歯内療法」と呼ばれ、歯の神経や血管が通っている根管という部分を清掃し、細菌を除去する治療です。虫歯が深く進行して神経まで達した場合や、神経が死んでしまった場合に必要となります。多くの方が「痛そう」「怖い」というイメージを持っていますが、実際には麻酔を使用するため、治療中の痛みはほとんどありません。むしろ、根管治療により、それまでの激しい痛みから解放されることが多いのです。また、根管治療により、抜歯せずに自分の歯を残せる可能性が高まります。この記事では、根管治療とは何か、どのような場合に必要なのか、治療の流れ、痛みの有無、通院回数、費用、そして治療後の注意点について詳しく解説します。正しい知識を持って、安心して治療を受けましょう。
根管治療とは
根管治療とは、歯の内部にある根管という細い管を清掃し、細菌を除去して密封する治療です。根管には、神経や血管が通っており、歯に栄養を供給しています。虫歯や外傷により、この根管内の神経が感染したり死んでしまったりした場合、根管治療が必要になります。
根管治療の目的は、感染した組織を完全に除去し、根管内を無菌状態にして密封することで、歯を保存することです。
どのような場合に根管治療が必要か
虫歯が神経まで達した場合
虫歯が深く進行し、歯髄(神経と血管の集まり)まで細菌が侵入すると、激しい痛みが生じます。このまま放置すると、感染が根の先まで広がり、膿が溜まります。根管治療により、感染した神経を除去し、痛みを取り除きます。
神経が死んでしまった場合
虫歯や外傷により、神経が死んでしまうことがあります。神経が死ぬと、一時的に痛みが消えることがありますが、細菌が繁殖し、根の先に膿が溜まります。これを放置すると、再び激しい痛みや腫れが生じます。
根の先に膿が溜まった場合
過去に神経を取った歯でも、根管内の細菌が完全に除去されていなかったり、再感染したりすると、根の先に膿が溜まることがあります。この場合、再度根管治療(再根管治療)が必要になります。
歯が割れたり、ひびが入った場合
外傷により歯が割れたり、ひびが入ったりすると、神経がダメージを受けることがあります。この場合も根管治療が必要になることがあります。
根管治療の流れ
根管治療は、複数回の通院が必要な複雑な治療です。
初日:診査と麻酔
まず、レントゲン撮影やCT撮影により、根管の状態を詳しく調べます。次に、局所麻酔を行います。麻酔により、治療中の痛みはほとんど感じません。
根管の開放
歯の上部から根管に到達するための穴を開けます。虫歯の部分も削り取ります。
感染した神経・組織の除去
リーマーやファイルという細い針金のような器具を使って、根管内の感染した神経や組織、細菌を除去します。根管は非常に細く、曲がっていることもあり、慎重な作業が必要です。
根管の清掃と拡大
根管内を洗浄液で洗い流しながら、徐々に太いファイルを使って根管を拡大し、形を整えます。根管内を無菌状態に近づけることが目標です。
仮の詰め物
根管内に消毒薬を入れ、仮の詰め物をして、初日の治療は終了です。根管内の細菌を完全に除去するため、通常は複数回、この清掃作業を繰り返します。
根管充填
根管内が十分に清潔になったら、根管を密封します。ガッタパーチャという材料を使って、根管の先端まで隙間なく充填します。これにより、再感染を防ぎます。
土台と被せ物
根管治療後の歯は、神経がないため脆くなっています。歯を補強するために、土台(コア)を立て、最終的に被せ物(クラウン)をします。被せ物により、歯の強度を回復させ、長期的に使用できるようにします。
治療中の痛みはあるのか
多くの方が心配する治療中の痛みですが、現代の根管治療では、麻酔を使用するため、治療中の痛みはほとんどありません。
麻酔の効果
局所麻酔により、治療部位の感覚が完全に麻痺します。器具が触れている感覚や、振動は感じることがありますが、痛みはありません。
麻酔が効きにくいケース
炎症が強い場合、組織が酸性に傾き、麻酔が効きにくくなることがあります。この場合、抗生物質で炎症を抑えてから治療したり、麻酔を追加したりして対応します。
治療後の痛み
治療後、麻酔が切れると、多少の痛みや違和感が生じることがあります。これは、治療による刺激で一時的に炎症が起こるためです。通常は数日で治まりますが、痛みが強い場合は、処方された痛み止めを服用します。
以前より痛みは軽減
根管治療を受ける前は、神経の炎症により激しい痛みがあることが多いです。根管治療により、その痛みの原因が除去されるため、治療後は楽になります。
通院回数と期間
根管治療の通院回数は、症状や根管の状態により異なります。
一般的なケース
軽度から中等度の場合、2回から4回の通院で終わることが多いです。期間は2週間から1ヶ月程度です。
複雑なケース
根管が複雑に曲がっている、感染が重度、再根管治療の場合などは、5回以上の通院が必要になることもあります。
通院間隔
通常は1週間に1回程度の間隔で通院します。根管内を消毒し、細菌を確実に除去するために、時間をかけて治療します。
根管治療の成功率
根管治療の成功率は、初回の治療で約90%以上と言われています。ただし、再根管治療の場合や、根管が非常に複雑な場合は、成功率が下がることがあります。
成功のためには、徹底した清掃と密封、そして最終的な被せ物により歯を保護することが重要です。
根管治療の費用
保険診療
根管治療は保険適用です。3割負担の場合、前歯で約3000円から5000円、奥歯で約5000円から1万円程度が治療費の目安です。これに、被せ物の費用が別途かかります。
自費診療
より精密な治療を希望する場合、マイクロスコープ(顕微鏡)を使用した根管治療や、ラバーダムの使用など、自費診療を選択することもできます。費用は歯科医院により異なりますが、1本あたり5万円から15万円程度が一般的です。
根管治療後の注意点
仮の詰め物が入っている間
仮の詰め物は取れやすいため、その歯で硬いものを噛まないようにしましょう。また、粘着性の高い食べ物も避けてください。
治療中の歯で噛まない
根管治療中の歯は脆くなっているため、強く噛むと割れる危険があります。反対側の歯で噛むようにしましょう。
痛みや腫れが出たら連絡
治療後に強い痛みや腫れが出た場合は、すぐに歯科医院に連絡しましょう。
治療を中断しない
根管治療を途中で中断すると、細菌が繁殖し、状態が悪化します。痛みがなくなっても、必ず最後まで通院しましょう。
被せ物は必須
根管治療後の歯は、被せ物をしないと割れやすく、長持ちしません。必ず被せ物まで完了させましょう。
根管治療後の歯の寿命
適切な根管治療と被せ物により、神経のない歯でも、数十年間使用できることは珍しくありません。ただし、神経のある歯に比べて脆くなっているため、定期的なメンテナンスが重要です。
再根管治療
過去に根管治療を受けた歯でも、再感染することがあります。根の先に膿が溜まった、痛みや腫れが出たなどの症状がある場合、再度根管治療(再根管治療)が必要になります。再根管治療は、初回の治療よりも難しく、時間がかかることが多いです。
根管治療を避けるために
根管治療が必要にならないようにするためには、予防が最も重要です。
定期検診
定期的な歯科検診により、虫歯を早期発見し、神経に達する前に治療できます。
丁寧な歯磨き
毎日の丁寧な歯磨きにより、虫歯を予防できます。
早めの治療
虫歯を放置せず、早めに治療することで、根管治療を避けられます。
まとめ
根管治療は、虫歯が神経まで達した場合や、神経が死んでしまった場合に必要な治療です。感染した神経や組織を除去し、根管を清掃・密封することで、歯を保存できます。治療中は麻酔を使用するため、痛みはほとんどありません。通院回数は2回から4回程度が一般的で、期間は2週間から1ヶ月程度です。治療費は保険適用で数千円から1万円程度です。治療後は仮の詰め物が取れないよう注意し、最後まで通院して被せ物まで完了させることが重要です。適切な根管治療により、抜歯を避け、自分の歯を長く使い続けることができます。定期検診と早めの治療により、根管治療が必要にならないよう予防しましょう。
親切丁寧な対応で、安心して通って頂ける怖くない、痛くない歯科医院を目指します!
阿倍野区昭和町おすすめ、ひだまり歯科、是非、ご来院ください。