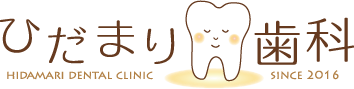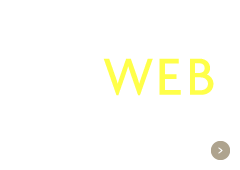睡眠時無呼吸症候群と歯科治療|いびきの裏に潜む危険なサイン

はじめに
「いびきがうるさい」「日中に強い眠気を感じる」「朝起きても疲れが取れない」こんな症状に心当たりはありませんか。それは単なる疲れやストレスではなく、睡眠時無呼吸症候群(SAS:Sleep Apnea Syndrome)という病気のサインかもしれません。
睡眠時無呼吸症候群は、睡眠中に何度も呼吸が止まったり浅くなったりする病気で、放置すると高血圧、心臓病、脳卒中などの重大な疾患のリスクを高めます。実は、この病気の治療に歯科が大きな役割を果たすことをご存知でしょうか。
この記事では、睡眠時無呼吸症候群とは何か、歯科でできる治療法、そして日常生活でできる予防策について詳しく解説します。
睡眠時無呼吸症候群とは
病気のメカニズム
睡眠時無呼吸症候群は、睡眠中に気道が狭くなったり塞がったりすることで、呼吸が止まる状態を繰り返す病気です。医学的には、10秒以上呼吸が止まる状態を「無呼吸」、呼吸が浅くなる状態を「低呼吸」と定義し、これらが1時間に5回以上起こる場合に睡眠時無呼吸症候群と診断されます。
呼吸が止まると、体は酸素不足を察知して目を覚まそうとします。本人は目覚めたことを自覚していなくても、脳は覚醒状態になり、深い睡眠が得られなくなります。この状態が一晩中繰り返されるため、睡眠時間は十分でも質の悪い睡眠になってしまうのです。
主な症状とサイン
睡眠時無呼吸症候群の代表的な症状は、大きないびき、睡眠中の呼吸停止、日中の強い眠気です。家族から「いびきがひどい」「息が止まっている時がある」と指摘されたことがある人は要注意です。
その他にも、朝起きた時の頭痛や口の渇き、集中力の低下、記憶力の低下、夜間頻尿、起床時の倦怠感なども典型的な症状です。重症の場合、運転中や会議中に突然眠ってしまうこともあり、日常生活に深刻な影響を及ぼします。
健康への深刻な影響
睡眠時無呼吸症候群を放置すると、さまざまな合併症のリスクが高まります。繰り返される低酸素状態と交感神経の活性化により、高血圧、不整脈、心筋梗塞、脳卒中のリスクが2倍から4倍に増加します。
また、日中の眠気による交通事故や労働災害のリスクも深刻な問題です。睡眠時無呼吸症候群の患者は、健康な人に比べて交通事故を起こす確率が約7倍高いという報告もあります。
さらに、糖尿病や高脂血症の悪化、うつ病、認知症のリスク増加との関連も指摘されており、全身の健康に多大な影響を与える疾患なのです。
睡眠時無呼吸症候群の原因
閉塞性睡眠時無呼吸症候群
睡眠時無呼吸症候群の約9割を占めるのが「閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSAS)」です。これは、睡眠中に舌や軟口蓋が喉の奥に落ち込んで気道を塞いでしまうことで起こります。
肥満、加齢、扁桃腺の肥大、舌が大きい、下顎が小さい、鼻づまりなどが原因となります。特に日本人を含むアジア人は、欧米人に比べて顎が小さい骨格的特徴があるため、肥満でなくても睡眠時無呼吸症候群になりやすいとされています。
中枢性と混合性
まれに、脳の呼吸中枢の異常によって起こる「中枢性睡眠時無呼吸症候群」や、閉塞性と中枢性の両方の特徴を持つ「混合性睡眠時無呼吸症候群」もあります。これらは医療機関での専門的な治療が必要です。
歯科でできる治療法
口腔内装置(マウスピース)療法
軽度から中等度の睡眠時無呼吸症候群に対して、歯科で行う効果的な治療法が「口腔内装置(OA:Oral Appliance)療法」です。これは、睡眠中に専用のマウスピースを装着することで、下顎を前方に移動させ、気道を広く保つ治療法です。
マウスピースは患者さん一人ひとりの歯型に合わせて作製されます。上下の歯にそれぞれ装着し、連結部分で下顎を数ミリ前方に固定する仕組みです。下顎が前に出ることで、舌や軟口蓋が喉の奥に落ち込むのを防ぎ、気道を確保します。
口腔内装置のメリット
口腔内装置には多くのメリットがあります。まず、携帯性に優れており、出張や旅行にも簡単に持ち運べます。CPAP(持続陽圧呼吸療法)という別の治療法と比べて、装置が小型で静かなため、家族への影響も少なくて済みます。
また、電源が不要で使用が簡単なため、継続しやすいという特徴もあります。適切に作製された口腔内装置は、軽度から中等度の症例において、無呼吸の回数を約50%から60%減少させる効果があると報告されています。
口腔内装置の適応条件
口腔内装置療法を行うには、いくつかの条件があります。まず、ある程度の本数の歯が残っていることが必要です。装置を固定するために、上下それぞれに少なくとも6本から8本の健康な歯が必要とされます。
また、重度の顎関節症や重度の歯周病がある場合は、治療が難しいことがあります。さらに、重症の睡眠時無呼吸症候群の場合は、口腔内装置だけでは十分な効果が得られないため、CPAPなど他の治療法が優先されます。
治療の流れ
歯科での治療は、まず医科で睡眠時無呼吸症候群の診断を受けることから始まります。医師の診断書を持って歯科医院を受診すると、保険適用で口腔内装置を作製できます。
初診時に口腔内の検査を行い、歯や顎の状態を確認します。問題がなければ、歯型を取り、2週間から3週間後に完成した装置を装着します。その後、数回の調整を経て、最適な下顎の位置を決定します。定期的なメンテナンスと効果の確認のため、3ヶ月から6ヶ月ごとの通院が必要です。
口腔内装置使用時の注意点
口腔内装置を使用する際の注意点もあります。装着初期は、顎の違和感や歯の圧迫感、唾液の増加などを感じることがありますが、多くの場合、1週間から2週間で慣れます。
また、長期使用により顎関節や噛み合わせに影響が出ることがあるため、定期的に歯科医師のチェックを受けることが重要です。装置は毎日使用後に洗浄し、清潔に保ちましょう。
その他の治療法との組み合わせ
CPAP療法
重症の睡眠時無呼吸症候群には、CPAP(持続陽圧呼吸療法)が第一選択となります。これは、睡眠中に鼻マスクを装着し、空気を送り込むことで気道を広げる治療法です。効果は高いですが、装置が大きい、音がする、マスクの違和感があるなどの理由で、継続できない人もいます。
CPAPに慣れない患者さんに対して、口腔内装置を代替療法として、または併用療法として使用するケースもあります。
外科的治療
扁桃腺が極端に大きい場合や、顎の骨格に明らかな異常がある場合は、外科的治療が検討されることもあります。扁桃摘出術や、顎を前方に移動させる手術などがありますが、侵襲が大きいため、他の治療法で効果が得られない場合の選択肢となります。
日常生活でできる予防と改善策
減量と適正体重の維持
肥満は睡眠時無呼吸症候群の最大のリスク要因です。体重を10%減らすだけでも、無呼吸の回数が大幅に減少することが報告されています。バランスの取れた食事と適度な運動を習慣化し、適正体重を維持しましょう。
横向きで寝る
仰向けで寝ると、重力によって舌が喉の奥に落ち込みやすくなります。横向きで寝ることで、気道が確保されやすくなり、いびきや無呼吸が改善することがあります。抱き枕を使用したり、背中にクッションを置いたりすると、横向き寝を維持しやすくなります。
アルコールと睡眠薬の制限
アルコールや睡眠薬は、喉の筋肉を弛緩させ、気道を塞ぎやすくします。特に就寝前の飲酒は避けましょう。どうしても睡眠薬が必要な場合は、医師に睡眠時無呼吸症候群があることを伝え、適切な薬を処方してもらいましょう。
禁煙
喫煙は気道の炎症を引き起こし、睡眠時無呼吸症候群を悪化させます。禁煙することで、気道の状態が改善し、症状の軽減につながります。
鼻づまりの改善
鼻づまりがあると口呼吸になり、症状が悪化します。アレルギー性鼻炎や副鼻腔炎がある場合は、耳鼻咽喉科で適切な治療を受けましょう。
まとめ
睡眠時無呼吸症候群は、単なるいびきの問題ではなく、全身の健康に深刻な影響を及ぼす疾患です。放置すると心臓病や脳卒中などのリスクが高まるため、早期発見と適切な治療が重要です。
歯科で作製する口腔内装置は、軽度から中等度の症例に対して効果的な治療法であり、CPAPに比べて使いやすく継続しやすいというメリットがあります。いびきや日中の眠気が気になる方は、まず医療機関を受診し、適切な診断と治療を受けることをおすすめします。
また、減量、横向き寝、禁煙、節酒など、日常生活の改善も症状の軽減に大きく貢献します。質の良い睡眠は、健康で充実した生活の基盤です。睡眠時無呼吸症候群の可能性に気づいたら、早めに専門医に相談し、適切な治療を始めましょう。
怖くない!痛くない!阿倍野区昭和町おすすめ、ひだまり歯科でリラックスしながら治療を受けましょう!
是非、ご来院ください。