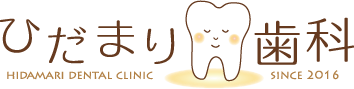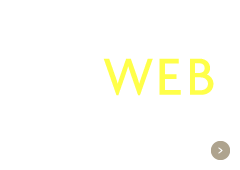歯磨き粉の量、ほんとはどれくらい?:年齢別の適量と正しい使い方

はじめに
歯磨きをする時、歯ブラシに歯磨き粉をどれくらいつけていますか。テレビCMでは、歯ブラシ全体にたっぷりと歯磨き粉が乗っている映像をよく見かけます。しかし、実はあの量は多すぎるのです。歯磨き粉の適量は、年齢や使用する製品によって異なり、思っているよりもずっと少ない量で十分です。多すぎると、泡立ちすぎて磨いた気になってしまったり、フッ素の過剰摂取につながったりする可能性があります。この記事では、歯科医師が推奨する歯磨き粉の適量と、効果的な使い方について詳しく解説していきます。
歯磨き粉の役割
清掃補助
歯磨き粉に含まれる研磨剤は、歯の表面の汚れや着色を除去する手助けをします。ただし、歯を清潔にする主役は歯ブラシの物理的な動きであり、歯磨き粉はあくまで補助的な役割です。
フッ素による虫歯予防
現代の歯磨き粉の最も重要な成分がフッ素です。フッ素は歯のエナメル質を強化し、むし歯を予防する効果があります。
適量のフッ素を定期的に歯に供給することが、むし歯予防の鍵となります。
口臭予防と爽快感
香味剤や清涼剤により、口の中がさっぱりし、爽快感が得られます。これは心理的にも、歯磨きの習慣を継続するモチベーションになります。
歯周病予防成分
製品によっては、歯周病予防成分や抗炎症成分が配合されているものもあります。
なぜ適量が重要なのか
多すぎると磨けていない
歯磨き粉を多くつけすぎると、泡立ちが多くなり、短時間で口がいっぱいになります。その結果、十分な時間をかけて磨く前に口をすすいでしまい、磨き残しが多くなります。
「泡立った=きれいになった」と錯覚してしまうのが、最大の問題です。
フッ素の過剰摂取リスク
特に子どもの場合、歯磨き粉を飲み込んでしまうことがあります。過剰なフッ素摂取は、フッ素症(歯のエナメル質に白い斑点ができる状態)の原因になる可能性があります。
適量を守ることで、このリスクを最小限に抑えられます。
経済的な無駄
必要以上に使うことは、単純に無駄です。適量で十分な効果が得られるため、過剰に使う必要はありません。
研磨剤による歯の摩耗
研磨剤を多く使いすぎると、長期的には歯の表面を傷つけ、エナメル質を摩耗させる可能性があります。
年齢別の適量
6か月から2歳まで
歯が生え始めてから2歳までは、切った爪程度の量(米粒大)が推奨されます。使用するフッ素濃度は、500ppm程度が適切です。
この時期はまだうがいができないため、飲み込んでも安全な量にすることが重要です。仕上げ磨きの後、ガーゼで拭き取る方法もあります。
3歳から5歳
3歳から5歳は、5ミリメートル程度(グリーンピース大)が目安です。フッ素濃度は500ppm程度を使用します。
この年齢でもまだ完全にうがいができない子もいるため、飲み込む量を考慮した適量が推奨されています。
6歳から成人
6歳以降は、1センチメートルから2センチメートル程度が適量です。フッ素濃度は1000ppm以上の製品を使用できます。
6歳は第一大臼歯(6歳臼歯)が生える大切な時期で、しっかりとしたむし歯予防が必要です。
高齢者
高齢者も基本的には成人と同じ量で問題ありませんが、根面むし歯のリスクが高まるため、高濃度フッ素(1450ppm)の使用が推奨されることもあります。
ただし、唾液が減少している場合は、泡立ちが気になることがあるため、量を調整することも検討します。
フッ素濃度による違い
低濃度(500ppm前後)
乳幼児向けの製品に多く、安全性を重視した濃度です。飲み込んでしまっても、リスクが低い設定になっています。
中濃度(950ppm~1000ppm)
子ども用から大人用まで幅広く使われる濃度です。日本では、この程度の濃度が一般的でした。
高濃度(1450ppm)
2017年から日本でも販売が解禁された高濃度フッ素配合の歯磨き粉です。むし歯予防効果がより高く、6歳以上に推奨されます。
ただし、6歳未満の使用は推奨されていません。
正しい歯磨き粉の使い方
適量を歯ブラシにつける
歯ブラシの毛先に、年齢に応じた適量の歯磨き粉をつけます。多すぎず、少なすぎず、適量を守ることが大切です。
丁寧にブラッシング
歯磨き粉をつけたら、最低でも2分から3分間、すべての歯を丁寧に磨きます。泡立ちが気になっても、我慢して時間をかけて磨きましょう。
うがいは少量の水で1回
歯磨き後のうがいは、コップ4分の1程度(15ミリリットル程度)の水で、1回だけ軽くすすぐのが理想的です。
何度も口をすすぐと、せっかくのフッ素が流れてしまいます。フッ素を口の中に残すことで、効果が持続します。
歯磨き後30分は飲食を控える
フッ素が歯に浸透し、効果を発揮するには時間が必要です。歯磨き後30分程度は、飲食を控えることをお勧めします。
よくある間違い
CMと同じ量を使う
テレビCMでは、見栄えの良さから歯ブラシ全体に歯磨き粉を乗せています。しかし、実際にはあの量は多すぎます。
CMはあくまで商品のイメージであり、適量を示しているわけではありません。
泡立ち重視
泡立ちが多いほど清潔になると思い込んでいる人がいますが、これは誤解です。泡立ちと清掃効果は直接関係ありません。
むしろ、泡立ちすぎると、十分に磨く前に口をすすいでしまう原因になります。
何度もすすぐ
歯磨き後、何度も口をすすぐと、フッ素が流れてしまい、効果が半減します。少量の水で1回軽くすすぐだけで十分です。
歯磨き粉なしは効果がない?
実は、歯磨き粉を使わなくても、歯ブラシによる物理的な清掃だけで、歯垢の除去は可能です。
ただし、フッ素によるむし歯予防効果が得られないため、フッ素入り歯磨き粉の使用が推奨されます。
特殊な状況での使用
矯正治療中
矯正装置をつけている場合、磨きにくい部分が多くなります。少量の歯磨き粉で時間をかけて丁寧に磨くことが重要です。
泡立ちが少ない方が、細かい部分まで見ながら磨けます。
知覚過敏がある場合
知覚過敏用の歯磨き粉を使用する場合も、適量を守ります。効果を高めるために、磨いた後に歯磨き粉を歯に塗布して数分置く方法もあります。
ホワイトニング後
ホワイトニング直後は、歯が敏感になっています。刺激の少ない歯磨き粉を、通常より少なめに使用することをお勧めします。
歯磨き粉の選び方
フッ素濃度を確認
年齢に応じた適切なフッ素濃度の製品を選びましょう。パッケージに記載されているppm値を確認します。
研磨剤の強さ
毎日使う歯磨き粉は、研磨剤が強すぎないものを選びましょう。特にエナメル質が薄い人や、知覚過敏がある人は注意が必要です。
目的に応じた選択
むし歯予防、歯周病予防、ホワイトニング、知覚過敏対策など、自分の目的に合った製品を選びます。
子ども用と大人用の違い
子ども用は、フッ素濃度が低く、味も甘めで、飲み込んでも安全性が高い設計になっています。年齢に応じた製品を使い分けましょう。
歯磨き粉以外のフッ素製品
フッ素ジェル
歯磨き後に使用するフッ素ジェルは、歯磨き粉よりも高濃度のフッ素を含みます。うがいができる年齢から使用でき、より効果的なむし歯予防が期待できます。
フッ素洗口液
うがいができる年齢であれば、フッ素洗口液も効果的です。歯磨き後に口に含んでうがいするだけで、フッ素を歯に供給できます。
歯科医院でのフッ素塗布
家庭でのフッ素ケアに加えて、3か月から6か月に一度、歯科医院で高濃度フッ素を塗布してもらうことで、より強力なむし歯予防効果が得られます。
子どもへの指導方法
視覚的に示す
「米粒大」「グリーンピース大」など、具体的な例えで量を示すと、子どもにも分かりやすいです。
親が管理する
幼児期は、親が適量を歯ブラシにつけてあげましょう。子ども自身に任せると、多くつけすぎてしまうことがあります。
習慣化する
毎日同じ量を使うことで、適量が習慣化します。ディスペンサータイプの歯磨き粉を使うと、量の管理がしやすくなります。
まとめ
歯磨き粉の適量は、年齢によって異なります。乳幼児は米粒大、幼児は5ミリメートル程度、6歳以降は1センチメートルから2センチメートル程度が目安です。
多すぎると泡立ちすぎて十分に磨けず、フッ素の過剰摂取のリスクもあります。適量を守り、丁寧にブラッシングし、うがいは少量の水で1回だけにすることで、フッ素の効果を最大限に活用できます。
テレビCMの量に惑わされず、正しい知識を持って、効果的な歯磨きを実践しましょう。小さな習慣の改善が、あなたの口腔健康を守る大きな力になります。
最新の設備と優しいスタッフが揃った、阿倍野区昭和町おすすめ、ひだまり歯科では怖くない、安心の治療を提供致します!
是非、ご来院ください。