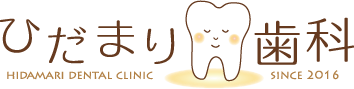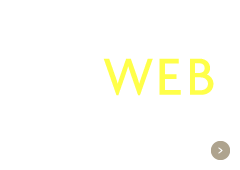歯の神経を取る治療とは?:根管治療の全てを詳しく解説

はじめに
歯科医院で「神経を取る必要があります」と言われて、不安を感じた経験はありませんか。歯の神経を取る治療は、正式には根管治療と呼ばれ、重度の虫歯や歯の損傷に対して行われる重要な処置です。神経を取ると聞くと怖いイメージがあるかもしれませんが、実際にはどのような治療なのか、なぜ必要なのか、治療後の歯はどうなるのかなど、正しい知識を持つことが大切です。この記事では、歯の神経を取る治療について、その目的、手順、メリットとデメリット、治療後の注意点まで詳しく解説します。不安を解消し、納得して治療に臨めるよう、わかりやすくご説明します。
歯の神経とは
歯の中心部には、歯髄と呼ばれる柔らかい組織があります。これが一般的に「歯の神経」と呼ばれるものです。歯髄には神経だけでなく、血管やリンパ管も含まれており、歯に栄養を供給し、痛みを感じるセンサーとしての役割を果たしています。
健康な歯では、歯髄が歯に栄養を与え、虫歯などの刺激に対して痛みという警告信号を発することで、私たちに異常を知らせます。また、歯の内部で細菌と戦う免疫機能も持っています。このように、歯髄は歯の健康維持に重要な役割を担っています。
神経を取る必要がある状況
重度の虫歯
虫歯が深く進行して歯髄にまで達すると、細菌感染により歯髄に炎症が起こります。この状態を歯髄炎と呼びます。初期段階では可逆性歯髄炎といって、適切な治療により回復する可能性もありますが、進行すると不可逆性歯髄炎となり、歯髄を除去する必要が出てきます。激しい痛みや、何もしなくてもズキズキする痛みがある場合、神経を取る治療が必要になることが多いです。
歯の破折や外傷
事故やスポーツで歯が折れたり、強い衝撃を受けたりした場合、歯髄が損傷して炎症を起こすことがあります。外見上は問題がないように見えても、内部で歯髄がダメージを受けていることもあります。時間が経ってから痛みが出てくることもあるため、歯に強い衝撃を受けた場合は、早めに歯科医院を受診することが大切です。
歯髄壊死
虫歯や外傷により歯髄への血液供給が途絶えると、歯髄が死んでしまいます。この状態を歯髄壊死と呼びます。痛みを感じなくなることもありますが、細菌が増殖して根の先に膿が溜まり、腫れや痛みが出ることがあります。このような場合も根管治療が必要です。
補綴治療の前処置
大きな被せ物を入れる際、歯を大きく削る必要がある場合、歯髄に近づきすぎて治療後に痛みが出るリスクがあります。そのようなケースでは、予防的に神経を取ることもあります。ただし、最近では可能な限り神経を残す方向で治療が行われることが多くなっています。
根管治療の手順
診断と麻酔
まず、レントゲン検査や症状の確認により、根管治療が必要かどうかを診断します。治療が必要と判断された場合、局所麻酔を行います。すでに神経が死んでいる場合は痛みを感じないこともありますが、周囲の組織への刺激を避けるため、通常は麻酔を使用します。
虫歯の除去とアクセス
虫歯を取り除き、歯の上部から歯髄にアクセスするための穴を開けます。この段階で、感染した歯質や古い詰め物なども完全に除去します。清潔な環境で治療を行うことが、成功の鍵となります。
歯髄の除去
専用の細い器具を使用して、歯髄を除去します。歯には通常1本から4本程度の根管があり、それぞれの根管内の歯髄を丁寧に取り除いていきます。根管は非常に細く、複雑な形状をしていることもあるため、時間をかけて慎重に行う必要があります。
根管の清掃と消毒
歯髄を除去した後、根管内を専用の薬液で洗浄し、消毒します。細菌や感染物質を徹底的に取り除くことが重要です。ファイルと呼ばれる器具で根管の壁を削りながら形を整え、同時に汚れを除去していきます。この工程を何度か繰り返します。
根管充填
根管内が十分にきれいになったら、ガッタパーチャという医療用ゴムのような材料で根管を隙間なく充填します。これにより、細菌が再び侵入するのを防ぎます。根管充填が完了したら、レントゲンで確認し、適切に詰められているかをチェックします。
土台と被せ物
根管治療後は、歯が脆くなっているため、土台を立てて被せ物をすることが一般的です。これにより、歯の強度を回復させ、長期的に使用できるようにします。
治療回数と期間
根管治療は、通常2回から4回程度の通院が必要です。根管の本数や感染の程度、症状の有無により回数は変わります。前歯は根管が1本のことが多いため比較的早く終わりますが、奥歯は根管が複数あり複雑なため、時間がかかることがあります。
1回の治療時間は30分から1時間程度です。根管内の消毒を確実に行うため、薬を詰めて数日から1週間程度様子を見ることもあります。急いで治療を進めると、後から痛みや腫れが出ることがあるため、適切な期間をかけて治療することが重要です。
神経を取った後の歯の変化
痛みを感じなくなる
神経を取った歯は、虫歯が進行しても痛みを感じません。これは一見メリットのようですが、問題の発見が遅れるという大きなデメリットでもあります。定期的な歯科検診がより重要になります。
歯が脆くなる
神経を取ると、歯への血液供給が途絶え、栄養が届かなくなります。その結果、歯が脆くなり、欠けたり割れたりしやすくなります。そのため、根管治療後は被せ物で歯を保護することが推奨されます。
歯の変色
時間が経つと、神経を取った歯が黒ずんでくることがあります。特に前歯の場合、審美的に気になることがあります。ホワイトニングやセラミックの被せ物で対応することも可能です。
根管治療のメリット
最大のメリットは、抜歯を避けて自分の歯を残せることです。歯を失うと、入れ歯やブリッジ、インプラントなどの治療が必要になり、費用も時間もかかります。また、周囲の歯にも負担がかかります。根管治療により歯を保存できれば、こうした問題を避けることができます。
また、治療により痛みから解放され、膿が溜まるなどの感染の拡大も防げます。適切に治療された歯は、長期間機能を維持することが可能です。
根管治療のデメリットと注意点
治療の成功率
根管治療の成功率は、初回治療で約90%、再治療で約70%程度とされています。根管の形状が複雑な場合や、感染が深刻な場合は、治療がうまくいかないこともあります。
治療後の痛み
治療直後は、周囲の組織が刺激されて痛みが出ることがあります。通常は数日で治まりますが、痛みが続く場合や腫れが出た場合は、すぐに歯科医院に連絡しましょう。
再治療の可能性
根管治療後も、細菌が完全に除去できていなかった場合や、新たに細菌が侵入した場合、再び感染が起こることがあります。その場合、再治療や場合によっては抜歯が必要になることもあります。
治療後のケア
根管治療後の歯を長持ちさせるためには、適切なケアが必要です。毎日の丁寧な歯磨き、デンタルフロスの使用、定期的な歯科検診とクリーニングを欠かさないようにしましょう。
また、硬いものを噛む際には注意が必要です。神経を取った歯は脆いため、氷や硬いナッツなどを噛むと割れる可能性があります。被せ物が外れたり欠けたりした場合は、すぐに歯科医院を受診してください。
神経を残す可能性
虫歯が神経に近い場合でも、必ずしも神経を取る必要があるわけではありません。最近では、MTAセメントなどの新しい材料を使用して、神経を保存する治療法も開発されています。神経を残せるかどうかは、虫歯の深さや感染の程度、症状の有無などにより判断されます。
神経を残すことができれば、歯の寿命を延ばせる可能性が高まります。早期発見・早期治療が、神経を残すための最善の方法です。
まとめ
歯の神経を取る治療、すなわち根管治療は、重度の虫歯や歯の損傷に対して、歯を保存するために行われる重要な処置です。治療には数回の通院が必要で、時間もかかりますが、抜歯を避けて自分の歯を残せるという大きなメリットがあります。神経を取った歯は脆くなり、痛みを感じなくなるというデメリットもありますが、適切なケアと定期検診により、長期間使い続けることが可能です。何より大切なのは、虫歯が神経に達する前に治療を受けることです。定期的な歯科検診を受け、早期発見・早期治療を心がけましょう。歯の神経を取る治療について不安がある場合は、遠慮せず歯科医師に質問し、納得した上で治療を受けることをおすすめします。
経験豊富な専門医による怖くない安心のおすすめインプラント治療、ひだまり歯科で理想の笑顔を手に入れましょう!
是非、ご来院ください。